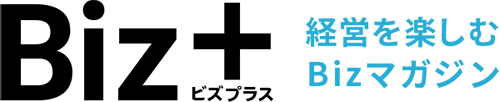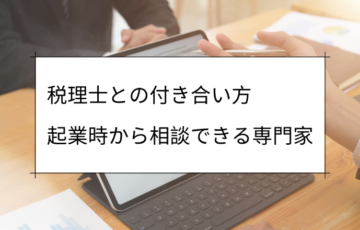「執行役員」、「専務」、「常務」などと聞くと、なんとなく「役員の人かもしれない」という印象を受けます。しかし、これらの地位を有する人々が会社法や法人税法上の「役員」に当たるかというと、必ずしもそうではありません。役員の要件や、その報酬決定方法については法律で厳格に要件が定められていて、これをよく理解しておかないと、場合によっては税法上不利な取扱いを受ける危険があります。本記事では、その報酬決定に関する注意事項などをみていきます。
1、役員とは
先にも述べた通り、一般的に企業で肩書として使われている「専務」「常務」「執行役員」などは、法律上の「役員」とは異なります。これらの役職は、仮に「役員」と名前についていても、取締役と兼務しているような場合を除けば「従業員」に過ぎません。
会社法上、「役員」とは「取締役、会計参与、監査役」を指します(会社法第329条[1])。
また、法人税法上、「役員」とは、法人の「取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの」とされています(法人税法第2条15号)。
これら法律上の「役員」は従業員と異なり、会社と雇用関係にはなく委任関係にあり、その報酬も従業員の給与とは異なる性質を有しています。
2、役員報酬を決める際の留意点
では役員の報酬を決めるに当たっては、どんなことに注意すれば良いでしょうか。
この点、役員報酬を決めるのが役員自身、特に社長自らその金額を自由に決められるとすると、ほしいまま不当に高い金額を設定するお手盛りがなされ、株主や債権者の利益を害する恐れがあります。
そこで、法律上、役員報酬の額は基本的に定款または株主総会の決議で決めるものとされています[2]ので、ご注意ください。
ただ、役員報酬の総額のみ株主総会決議等で決めておき、個々の役員報酬の内訳については取締役会等に一任されることが実務上は少なくありません。
この点、上場会社については、2021年会社法改正[3]により、株主総会等において個々の取締役の報酬内容が具体的に定められていない場合には、その内容に関する決定方針を定めることが義務付けられました[4]。
3、役員報酬と給与の違い
役員報酬をいつでも社内で自由に決定し経費として計上出来るようにしてしまうと、会社の業績が好調なときには役員報酬を多く払って経費を多く計上し、業績を本来より悪化したように見せかけるといった、利益操作による脱税も可能になってしまいます。
そこで、従業員に支払う給与は人件費として原則全額損金算入できるのに対し、役員報酬は、一定の要件を満たさない限り、原則として損金算入できません。
4、役員報酬の損金算入
しかし、役員報酬の額は小さくはありません。節税対策上、できれば経費として損金参入したいところです。この点、法律上、以下の3つの場合には例外的に役員報酬も損金参入できます。
◆定期同額給与
◆事前確定届出給与
◆業績連動給与
1つずつ見てみましょう。
◆定期同額給与の場合
定期同額給与とは、役員への報酬が1ヵ月以下の一定期間毎に定額で支給される場合をいいます。
これは従業員の給与と同様に同一額を定期的に支払うものですが、事業年度開始会計期間開始の日から3ヶ月経過後の変更要件は厳しい[6]ので、慎重に決定する必要があります。
特に設立開始直後はどれぐらい役員報酬を支給すればいいのか判断がつきにくく、つい毎月の利益に応じて変額支給してしまいたくなります。しかしそれでは損金不算入となってしまいますから、期首の頃はある程度大まかに見積もっておいて、年度開始3か月以内の間に様子をみて増減額するのが安全でしょう。
◆事前確定届出給与の場合
所轄の税務署長に対し、一定の時期に、個々の役員ごとの報酬支給時期と支給金額を明記した「事前確定届出給与に関する届出書」の届出を行う場合も、例外的に損金算入が認められます[7]。
参考: 国税庁HPNo.5211 役員に対する給与 国税庁 事前確定届出給与
この場合、①株主総会等の決議日もしくは職務執行開始日から1ヵ月を経過した日、②会計期間開始日から4ヶ月を経過した日のうち、どちらか早い日が提出期限となります
ただし、損金算入が認められるためには、必ず届け出た金額の通りに支給しなくてはなりません。たとえば200万円と届け出たのに250万円支払ったという場合、250万円全額が損金不算入の扱いになってしまいます。
思ったより業績が伸びず、役員に既定の報酬を支払えなくても損金として扱えませんし、逆に好調な業績に比して著しく低い報酬を設定していたために、役員へのインセンティブを与えようと報酬額を増やせば節税ができなくなります。
このような不測の事態が生じることを防ぐためにも、会社としては、その期中に生じる損益の金額等をできるだけ正確に予想し、計画的に役員報酬を決定しましょう。
もちろん、後日、やむを得ない場合などの変更も可能ですが、こちらも定期同額給与同様、要件が厳しく定められているので注意してください。
◆業績連動給与の場合
業績連動給与は、平成29年税法改正前には「利益連動給付」と呼ばれていたもので、その名の通り、利益に関する指標を基礎とした業績に連動して給付される給与です[8]。
報酬が業績に連動して決定されるため、前二者と異なり、金額が確定していないという特徴があり、こちらも条件を満たせば損金参入が可能になります。
ただ、業績連動給与として認められるためには、基準となる利益指標及び報酬の算定方法を決定し、その内容を有価証券報告書に記載し、開示する必要があります。すなわち、原則として有価証券報告書の提出が必要な上場会社等に限定されており、中小企業にはあまり縁がありません。
その他にも「同族会社に該当しない内国法人であること」をはじめ細かい要件が規定されているうえ、そもそも上場会社に関しては、役員報酬全般に関して令和3年3月1日から施行される改正会社法での改正事項がありますので、専門家に相談したり、国税庁ホームページを確認することをお勧めします。
5、まとめ
役員報酬は自由に損金算入させてしまうと、恣意的な利益操作が可能になるため、例外的に損金算入が認められる場合の要件は厳しく定められています。適切な役員報酬を正しい手続きに則って支払うことで、損金算入を利用して上手に節税しましょう。
弁護士業、事務職員等を経て、現在は主にフリーのライター。得意ジャンルは一般法務のほか、男女・夫婦間の問題や英語教育など。英検1級。
[1] 会社法施行規則第2条第3項3号ではさらに「取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者」と規定されています。
[2] 会社法第361条、第379条、第387条ほか
[3] 法務省:会社法の一部を改正する法律について (moj.go.jp)
[5] 参考:法人税法第34条第1項 国税庁 役員に対する経済的利益
[6] 役員の地位の変更や経営状況の著しい悪化等、やむを得ない事情がなければ変更が難しい。詳細は(先出)国税庁HPNo.5211 役員に対する給与 参照。
[8] 参考:法人税法第34条第3項 国税庁 算定方法の内容の開示(業績連動給与)